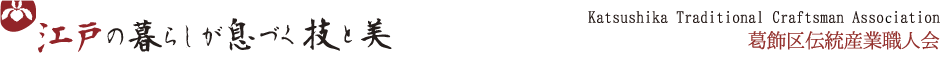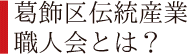金屏風のこばやし

灯火が消えるのふせぐ風除けとして中国で生まれた屏風。
それが日本に渡り、日本の技術や文化と融合し、さまざまな調度品が作られるようになりました。
特に、日本で独特の進化を遂げたのが、蝶番(ちょうつがい)の部分。それまでは革ひものようなもので結んでいただけだったものが、和紙を使ったあい折りという技法が発明され、これにより360度、表裏関係なく、折れるようになったのです。その結果、継ぎ目がわかりにくくなり、絵を描きやすくなり、たくさんの屏風絵画家が日本で輩出されました。
一方、絵の描かれていない金屏風は、金箔の絢爛さと、無地であることのつつましさを兼ね備え、結婚式などのおめでたい席で主役を引き立てる道具として、使われるようになります。
金屏風は六曲一隻(6枚組)と数えられ、通常の使い方であれば、20年は持つといわれます。良い品であれば、たとえ表面が傷ついても、何度でも修理が可能であり、また、そうして長い時を使い続けることが縁起が良いとされています。
それが日本に渡り、日本の技術や文化と融合し、さまざまな調度品が作られるようになりました。
特に、日本で独特の進化を遂げたのが、蝶番(ちょうつがい)の部分。それまでは革ひものようなもので結んでいただけだったものが、和紙を使ったあい折りという技法が発明され、これにより360度、表裏関係なく、折れるようになったのです。その結果、継ぎ目がわかりにくくなり、絵を描きやすくなり、たくさんの屏風絵画家が日本で輩出されました。
一方、絵の描かれていない金屏風は、金箔の絢爛さと、無地であることのつつましさを兼ね備え、結婚式などのおめでたい席で主役を引き立てる道具として、使われるようになります。
金屏風は六曲一隻(6枚組)と数えられ、通常の使い方であれば、20年は持つといわれます。良い品であれば、たとえ表面が傷ついても、何度でも修理が可能であり、また、そうして長い時を使い続けることが縁起が良いとされています。
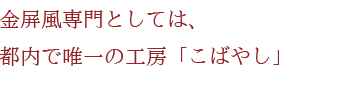
シュッという衣擦れのような音が、繰り返し、広い空間にこだまする。
金色の表紙(おもてがみ)が、まるで吸いつくように、ひとすじのよれもなく、八尺六曲(約縦2.5m×幅4m)の金屏風へと仕上がっていく。
ここは都内で唯一の金屏風専門の工房「こばやし」である。床は板張りで、しかかり中のものや道具類がかなりの量、保管されているにもかかわらず、広々としている。なにより、天井が高い。まるで劇団の稽古場かスタジオのようだ。この工房で、伝統工芸士の小林興司さんは、娘さんの早羽子さんと二人で黙々と作業をしている。二人で作業するようになって、もう5年以上になるという。多い日は一日に100枚もの表紙を貼ることもある。まず、その仕事量に驚くと、「職人はね。難しいことはやらないんです。器用さより、スピード。単純なことを間違えず、どれだけ素早くやれるかなんですよね」と穏やかな声で小林さんが答える。
確かに、金屏風は見た目はシンプルだ。しかし、その製作工程は大きく分けて11もの工程がある。骨しばり、ベタ張り、蝶番、みのがけ、下ぶくろ、中ぶくろ、上ぶくろ、裏張り、表張り、前おうで、そして最後の金具付けと続く。そのうちの一つの工程でも失敗すれば、すべてが台無しになる。
これは十分、複雑で難しい仕事だと思ったのが、顔に出たのだろうか、「強いていうなら、蝶番が少し難しいかな」とこちらを見て、小林さんは笑った。
「あい折り」という本格的な金屏風に使われる和紙を使った蝶番は、両側から360度開くという、ちょっと不思議な仕掛けだ。古玩具のパタパタとか、かったん等に使われている仕掛けといえば、わかる人も多いだろう。
「ゆるんではダメ、きつくてもダメ、そのちょうどいい塩梅が大事。でも、丁寧にやればいいだけ。そんなに難しくはないですよ」と小林さんはあくまで謙虚である。
金色の表紙(おもてがみ)が、まるで吸いつくように、ひとすじのよれもなく、八尺六曲(約縦2.5m×幅4m)の金屏風へと仕上がっていく。
ここは都内で唯一の金屏風専門の工房「こばやし」である。床は板張りで、しかかり中のものや道具類がかなりの量、保管されているにもかかわらず、広々としている。なにより、天井が高い。まるで劇団の稽古場かスタジオのようだ。この工房で、伝統工芸士の小林興司さんは、娘さんの早羽子さんと二人で黙々と作業をしている。二人で作業するようになって、もう5年以上になるという。多い日は一日に100枚もの表紙を貼ることもある。まず、その仕事量に驚くと、「職人はね。難しいことはやらないんです。器用さより、スピード。単純なことを間違えず、どれだけ素早くやれるかなんですよね」と穏やかな声で小林さんが答える。
確かに、金屏風は見た目はシンプルだ。しかし、その製作工程は大きく分けて11もの工程がある。骨しばり、ベタ張り、蝶番、みのがけ、下ぶくろ、中ぶくろ、上ぶくろ、裏張り、表張り、前おうで、そして最後の金具付けと続く。そのうちの一つの工程でも失敗すれば、すべてが台無しになる。
これは十分、複雑で難しい仕事だと思ったのが、顔に出たのだろうか、「強いていうなら、蝶番が少し難しいかな」とこちらを見て、小林さんは笑った。
「あい折り」という本格的な金屏風に使われる和紙を使った蝶番は、両側から360度開くという、ちょっと不思議な仕掛けだ。古玩具のパタパタとか、かったん等に使われている仕掛けといえば、わかる人も多いだろう。
「ゆるんではダメ、きつくてもダメ、そのちょうどいい塩梅が大事。でも、丁寧にやればいいだけ。そんなに難しくはないですよ」と小林さんはあくまで謙虚である。

▲真剣な面持ちで表紙を貼る小林さん。

▲貼りつけ作業のペースに合わせ糊付けをする。
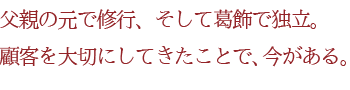
父親である先代が台東区入谷に屏風店を開き、その後、昭和48年に家族で葛飾に移る。小林さんが父親に弟子入りしたのは、学校を出て、さまざまな職業を経てからだったという。
早くから父の元で修行し、一人前になっていた兄がいたから、自分は「職人」になるという意識が薄かったかもしれないと当時を振り返る。
その小林さんが金屏風専門の職人として、独立したのは平成7年。当時から金屏風専門という人は、東京にはいなかった。
「父は、屏風だけでなく、襖などの注文を受けていたんです。僕はそうした取引先とのしがらみもなかったから、思い切れたんでしょうね。もちろん、金屏風だけじゃ、食えないといわれましたよ。でも、自分は器用じゃないから、あれもこれもはやれないという思いがあった」
まわりが心配したのには、当時の時代背景もある。金屏風市場は、ホテルが乱立したバブル期に最盛期を迎え、その後は急速に市場が衰えていったのだ。案の定、営業的にはきびしい日々が続いた。
自分でダイレクトメールを作り、ホテルやイベント会場などに送ったりもしたが、なかなか注文には結びつかなかった。もちろん、代理店に営業をお願いすれば、経営は楽になるのはわかっていた。しかし、小林さんはお客さんとの直接取引きにこだわったという。
早くから父の元で修行し、一人前になっていた兄がいたから、自分は「職人」になるという意識が薄かったかもしれないと当時を振り返る。
その小林さんが金屏風専門の職人として、独立したのは平成7年。当時から金屏風専門という人は、東京にはいなかった。
「父は、屏風だけでなく、襖などの注文を受けていたんです。僕はそうした取引先とのしがらみもなかったから、思い切れたんでしょうね。もちろん、金屏風だけじゃ、食えないといわれましたよ。でも、自分は器用じゃないから、あれもこれもはやれないという思いがあった」
まわりが心配したのには、当時の時代背景もある。金屏風市場は、ホテルが乱立したバブル期に最盛期を迎え、その後は急速に市場が衰えていったのだ。案の定、営業的にはきびしい日々が続いた。
自分でダイレクトメールを作り、ホテルやイベント会場などに送ったりもしたが、なかなか注文には結びつかなかった。もちろん、代理店に営業をお願いすれば、経営は楽になるのはわかっていた。しかし、小林さんはお客さんとの直接取引きにこだわったという。

▲互いの呼吸が合わないと一瞬ですべてが台無しになる。
バブルの時代に、多くの屏風店が代理店に依存し、急成長した結果、バブル崩壊と共に姿を消していったのを見ていたからだ。
「10年間で、大手といわれた屏風店はすべて消えてしまいました。バブルの時代には確かに金屏風が飛ぶように売れたんですよ。でも、その方がおかしかったんですよね」
その後もさまざまな誘いはあったが、数は少なくとも直接、注文をくれるお客さんを大切にする小林さんの姿勢はぶれなかった。やがて、その地道な努力が大きな信頼を築くことになる。品質にこだわる国立劇場や明治座をはじめ、一流ホテルなどから仕事が舞い込むようになったのだ。
「直接、お客さんとやり取りしているから、修理もすぐに対応できるし、お互いに納得できる仕事ができる。自分ができる範囲しか手は広がらないけど、それで十分です」と営業姿勢もあくまで謙虚だ。
「10年間で、大手といわれた屏風店はすべて消えてしまいました。バブルの時代には確かに金屏風が飛ぶように売れたんですよ。でも、その方がおかしかったんですよね」
その後もさまざまな誘いはあったが、数は少なくとも直接、注文をくれるお客さんを大切にする小林さんの姿勢はぶれなかった。やがて、その地道な努力が大きな信頼を築くことになる。品質にこだわる国立劇場や明治座をはじめ、一流ホテルなどから仕事が舞い込むようになったのだ。
「直接、お客さんとやり取りしているから、修理もすぐに対応できるし、お互いに納得できる仕事ができる。自分ができる範囲しか手は広がらないけど、それで十分です」と営業姿勢もあくまで謙虚だ。

▲少しのゆがみもなく表紙が木枠に吸い付いていく。その指先のスピードは驚くほど速い。
屏風は、そもそも灯火が消えるのふせぐ風除けとして中国で生まれたもの。それが日本に渡り、仕切りや調度品など、さまざまな道具へと進化をとげる。その一つが、金箔の絢爛さと、無地のつつましさを兼ね備え、結婚式などのおめでたい席で主役を引き立てる道具として使われるようになった金屏風である。
その大きさは2mを超え、実は小林さん一人では表紙を貼るのもままならない。どうしても誰かのサポートが必要になる。
独立後、金屏風職人としての小林さんを支え、手伝ってきたのは、ずっと奥様だったという。金屏風は無地であるがゆえに、ほんの少しのたわみでさえ、光の反射が変わるので、商品価値がなくなってしまう。もちろん、ヨレやシワなどは一切許されない。だから、たがいの呼吸が合わないと、良い仕事はできないという。その意味で、夫婦である奥様は最良のパートナーであったのだろう。職人夫婦が息を合わせてこしらえた金屏風が、若い夫婦の門出を飾るというのも、伝統工芸の世界らしい粋な話である。そうやって日本文化はつながってきたのだという思いを深くする。
残念ながら、その奥様はもういらっしゃらない。奥様に先立たれてしまった小林さんを、何も言わずに手伝ってくれるようになったのが、冒頭でもご紹介した愛娘の早羽子さんである。
子供の頃から、父親と母親が黙々と続ける作業を見てきたのだろう、傍から見ていても、二人の息はぴったり合っているように見える。
小林さん自身はどう思っているのかという質問をなげかけようとしてやめた。黙々と作業する小林さんの背中が、もうその答えを語っていたからである。
その大きさは2mを超え、実は小林さん一人では表紙を貼るのもままならない。どうしても誰かのサポートが必要になる。
独立後、金屏風職人としての小林さんを支え、手伝ってきたのは、ずっと奥様だったという。金屏風は無地であるがゆえに、ほんの少しのたわみでさえ、光の反射が変わるので、商品価値がなくなってしまう。もちろん、ヨレやシワなどは一切許されない。だから、たがいの呼吸が合わないと、良い仕事はできないという。その意味で、夫婦である奥様は最良のパートナーであったのだろう。職人夫婦が息を合わせてこしらえた金屏風が、若い夫婦の門出を飾るというのも、伝統工芸の世界らしい粋な話である。そうやって日本文化はつながってきたのだという思いを深くする。
残念ながら、その奥様はもういらっしゃらない。奥様に先立たれてしまった小林さんを、何も言わずに手伝ってくれるようになったのが、冒頭でもご紹介した愛娘の早羽子さんである。
子供の頃から、父親と母親が黙々と続ける作業を見てきたのだろう、傍から見ていても、二人の息はぴったり合っているように見える。
小林さん自身はどう思っているのかという質問をなげかけようとしてやめた。黙々と作業する小林さんの背中が、もうその答えを語っていたからである。
6件の商品がございます。