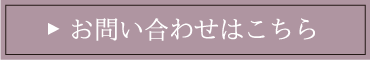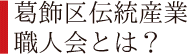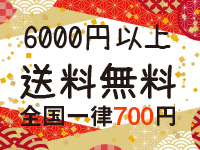竿しば
お世話になりました。
仕事を納めさせていただきました。
以下は葛飾の伝統産業の記録として残します。

江戸和竿は、天然の竹を用いた「継ぎ竿」のことで、江戸時代の享保年間に江戸で作られました。その後江戸時代後期に一大発展をとげ、江戸独特の「棧取り竿」など数多くの名品を生み出してきています。
今日の江戸和竿職人の系譜は、天明年間創業の泰地屋東作に遡るといわれています。
江戸和竿の特徴は、あらゆる魚の種類に応じた竿を制作していることと、竹の表皮を生かした漆仕上げにあります。
製造はすべて手作業で、工具も長い伝統の中で竿師の知恵の積み重ね、生まれたものを使用しています。
今日の江戸和竿職人の系譜は、天明年間創業の泰地屋東作に遡るといわれています。
江戸和竿の特徴は、あらゆる魚の種類に応じた竿を制作していることと、竹の表皮を生かした漆仕上げにあります。
製造はすべて手作業で、工具も長い伝統の中で竿師の知恵の積み重ね、生まれたものを使用しています。

まだ、13歳だった昭和20年の空襲で両親を失い、自身も大きな傷を負った芝崎さんは、翌21年に知人に紹介されて、和竿師のところに弟子入りをします。昭和40年に葛飾区新小岩で独立し、現在まで伝統の和竿を作り続けています。
[平成6年]葛飾区伝統工芸士 認定
[平成6年]葛飾区伝統工芸士 認定
良い竹は少なく、たとえ良い竹が見つかっても何本かの竹を継いで釣竿をつくるので、竹の硬さや太さが異なる物は使えません。だから良い竿をつくるため、材料探しに大変苦労します。
また竿を作るときは、お客さんの注文に合わせるだけでなく、釣竿がお客さんの手に合うよう、つまり釣り方や技量に合うよういつも心掛けています。和竿でしたら、修理、改造、火入れ承ります。

▲葛飾のフェアにて実演中の芝崎さん。

▲釣り人が憧れる「竿しば」の焼印。

▲継ぎが多く、節の間隔が揃っている。まさに名竿中の名竿。
昭和7年 南千住生まれ
昭和21年 知人の紹介で竿師に弟子入り
昭和40年 新小岩で独立
昭和47年 現在地に開店、現在に至る
昭和21年 知人の紹介で竿師に弟子入り
昭和40年 新小岩で独立
昭和47年 現在地に開店、現在に至る
2件の商品がございます。