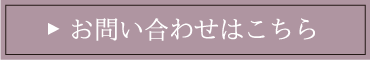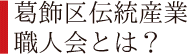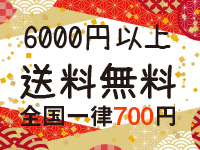近藤組紐製造所

東京組紐の起源は、江戸時代以前にさかのぼるといわれておりますが、徳川幕府の開設により、武家の中心地として武具の需要が高まり、組紐の生産が盛んとなりました。
江戸初期の組紐は、武士の生業として伝えられてました。
しかし、中期以降は一般庶民に普及し、実用的な物から、しだいに華美、精巧なものが作られるようになりましたが、幕府の度々の奢侈禁止令もあってか、さりげない「粋」を好む気風が生まれ、「わび」や「さび」の要素を加えた精緻なものへと発展しました。
今日でも、江戸の伝統を保持して手作りされ、その渋い味わいと気品の高さに特徴があります。
江戸初期の組紐は、武士の生業として伝えられてました。
しかし、中期以降は一般庶民に普及し、実用的な物から、しだいに華美、精巧なものが作られるようになりましたが、幕府の度々の奢侈禁止令もあってか、さりげない「粋」を好む気風が生まれ、「わび」や「さび」の要素を加えた精緻なものへと発展しました。
今日でも、江戸の伝統を保持して手作りされ、その渋い味わいと気品の高さに特徴があります。

近藤さんは二代目で、創業者のお父さんが昭和5年に現在の地に独立したのが始まりだという。組紐には、さまざまな種類があり、組むための作業台も、丸台、角台、高台、綾竹台などの種類がある。
近藤さんは、昭和29年より父親の仕事を手伝うようになり、主に高台で、平打ちの組紐を手がけている。特に瓢箪柄は近藤さん独自の柄と言われており、展示会に出ると、常に注目を浴び続けている。
[平成8年]葛飾区伝統工芸士 認定
近藤さんは、昭和29年より父親の仕事を手伝うようになり、主に高台で、平打ちの組紐を手がけている。特に瓢箪柄は近藤さん独自の柄と言われており、展示会に出ると、常に注目を浴び続けている。
[平成8年]葛飾区伝統工芸士 認定
自慢の柄は瓢箪柄で、紐に対して瓢箪がちょっと曲がったものです。
思い出深い仕事は、武蔵御嶽神社に奉納されている両面亀甲組紐を帯締めのようにして組み上げたことです。
思い出深い仕事は、武蔵御嶽神社に奉納されている両面亀甲組紐を帯締めのようにして組み上げたことです。

▲高台で平組紐を組む近藤さん。

▲左に並んでいるのが、平家納経の紐を復刻したもの。

▲色鮮やかな帯締めの数々。すべて近藤さんが一人で組み上げたものだ。
昭和7年葛飾区四つ木生れ
東京都伝統工芸士
葛飾区伝統工芸士
東京都伝統工芸士
葛飾区伝統工芸士
※店舗の都合上、ネットでのお取り扱いはございません。お問い合わせは下のフォームから、お気軽にどうぞ。