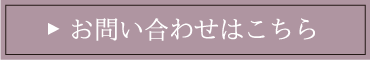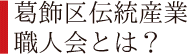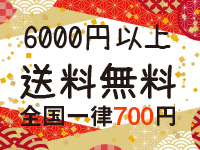西山慎二 夢雲

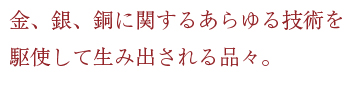
帝釈天でお馴染みの葛飾柴又の西にある高砂は、京成線の乗り換えの要所としても知られている。
この駅から南に徒歩10分ぐらい歩いたところに、西山慎二さんの工房はある。
西山さんは、東京銀器における鍛金を生業とする銀細工職人の家に、昭和27年3月、8人兄弟の5男として生まれた。
銀細工には、鍛金、彫金、鋳物、その他、さまざまな種類がある。そのどれをとっても一つの立派な伝統工芸であるが、西山家では鍛金だけでなく多くの技法を学ぶことが是とされたのだそうだ。
若い時から学ぶことを求められたからなのか、柔和な笑顔に、穏やかで物静かな口調の西山さんは、職人というよりは、どこか研究者のような雰囲気も感じさせる。
「まあ、仕事が広がるからということだったんじゃないかと思いますけどね。ただ、金属工芸において由緒正しい技術を継承しているという意識は父親の中にはあったのかな」
そう言いながら、見せてくれたのは古い書物。
そこには東京美術学校(現在の東京芸大)に明治28年に鍛金をはじめとする技術を学ぶ工芸科が設置された経緯が書かれており、そこに携わった金属工芸の技術者たちの系譜が記されている。その系譜が西山家に繋がっている。

▲松脂を詰め、浮かし彫りする作業。

▲写真では判然としないが、鯉の柄。

▲手製のタガネで、柄を一つ一つ浮き上がらせていく。

▲ロウ付けの作業台。数種類のバーナーを使い分ける。

▲なぜにカブトムシ?
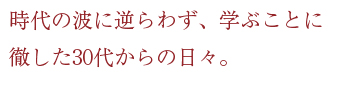
中学校を卒業すると、他の兄弟と同じように、父の三郎氏に弟子入りすることになるが、夜は都立工芸高校金属工芸科に4年間通い、さまざまな技法について学んだという。
「銀器は、こうでなければいけないという決まりがないんです。だから、自由にできる。そこが楽しいし、難しいところでもあります。頼まれれば、いろいろ作ってきました。印刷機械の模型を作ったり、素材も銀だけでなく、プラチナ、金、銅、いろいろ」
30歳までは、親兄弟と共に工房で仕事に励んだ。競馬の優勝トロフィーや在留米軍向けの銀食器、金杯にいたるあらゆる物を作ったと当時を振り返る。
しかし、いつしか大量生産、大量消費という時代の波が押し寄せ、仕事が急速に減っていった。
そこで西山さんは、以前より興味があったジュエリー関係の会社に職人として就職することになった。当時は、まだ、若かったし、もっともっといろんなことを学びたかったと話す。機械化も進んでいる大きな会社だったので、原型作り、仕上げ、石留から修理技法まで学ばせてもらった。
「修理はとても面白くて、初めての連続だったけど、それまでの経験が生きる場面も多かったんです。また、私が持っている技術やアイデアを活かし、喜ばれたり。それが楽しかった」
そうして、20年ほど勤めたが、しかし、またしても時代は変わる。
生産が人件費の安い海外に持っていかれてしまい、会社の景気が傾いてしまった。
皮肉なことに、今度は手仕事の伝統工芸が見直されるようになってきたのである。そこで西山氏は、お世話になった会社を辞し、兄の工房を手伝うようになった。
そして、いよいよ独立起業し、自身の工房「夢雲」を立ち上げることになったのである。
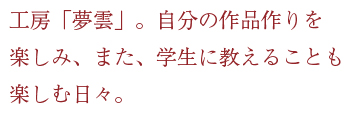

▲水滴。書道に使われる道具。

▲蝶のペンダント。幅2㎝にも満たない小ささなのに、羽が稼働する。

▲人気があるという折り鶴のペンダント。
西山さんが、これまでの人生でもっとも思い出深い出来事は、初めて作った作品を応募した東京銀器組合第一回金銀工芸新作コンクールにて「東京都中小企業団体中央会賞」を受賞した時のことだという。
というのも、その時に父であり、師匠の三郎氏が、ものすごく喜んでくれたのだとか。
「同じコンクールで、兄貴も別な賞をとってね。兄弟で受賞したからなんでしょう、ものすごく喜んでくれたんです。父があんなに喜んでくれるとは思わなかったんで、印象深いんですよ」
今、西山さんは、自身の工房「夢雲」を営み、他の兄弟たちも、東京銀器のマイスターとして、それぞれ活躍している。
「これでよかったと思います。十分、学ばせてもらったから、もう、あせることもなく自分の作品づくりに打ち込める環境が整いましたしね」
現在、西山さんは、製作に励む一方、母校の都立工芸高校からインターンシップを受け入れ、生徒たちに技術指導もしている。弟子入りを志願する生徒も時々いるという。
「興味を持って、学びに来てくれるのはうれしいですよね。この時代じゃ、弟子はとれないし、自分の持っている技術も限られた時間じゃ教えきれないけど、その代わりに良い物を作って残せばそこから学んでもらえるんじゃないかと思っています」
だから、西山さんは、今、作りたいものがたくさんあるという。
「その一つが、一枚絞りの湯沸かし。注ぎ口から弦を付けるミミまで打ち出す鍛金の絞り技法は、西山家の得意とするところなんです」
鍛金のしぼり技法は、平面の金属板を数えきれないほど、何回も槌で叩きのばして、立体に仕上げていく。この技法を父から受け継ぎ、長けていたのが、兄であり、その兄が、当面の目標であり、一番のライバルとのことだ。
「兄貴にできるんなら、自分にもできると思えるんですよね。超えられるかどうかはわからないけど、同じようにやってみたいという思いがあるんです」
時代の波に翻弄されてきた兄弟が、こうして同じ技術を追い求め続けることで、繋がっていられるというのは、すごいことである。
いつできるかわからないというが、西山さんの湯沸かしの仕上がりを見る日が心より楽しみである。
というのも、その時に父であり、師匠の三郎氏が、ものすごく喜んでくれたのだとか。
「同じコンクールで、兄貴も別な賞をとってね。兄弟で受賞したからなんでしょう、ものすごく喜んでくれたんです。父があんなに喜んでくれるとは思わなかったんで、印象深いんですよ」
今、西山さんは、自身の工房「夢雲」を営み、他の兄弟たちも、東京銀器のマイスターとして、それぞれ活躍している。
「これでよかったと思います。十分、学ばせてもらったから、もう、あせることもなく自分の作品づくりに打ち込める環境が整いましたしね」
現在、西山さんは、製作に励む一方、母校の都立工芸高校からインターンシップを受け入れ、生徒たちに技術指導もしている。弟子入りを志願する生徒も時々いるという。
「興味を持って、学びに来てくれるのはうれしいですよね。この時代じゃ、弟子はとれないし、自分の持っている技術も限られた時間じゃ教えきれないけど、その代わりに良い物を作って残せばそこから学んでもらえるんじゃないかと思っています」
だから、西山さんは、今、作りたいものがたくさんあるという。
「その一つが、一枚絞りの湯沸かし。注ぎ口から弦を付けるミミまで打ち出す鍛金の絞り技法は、西山家の得意とするところなんです」
鍛金のしぼり技法は、平面の金属板を数えきれないほど、何回も槌で叩きのばして、立体に仕上げていく。この技法を父から受け継ぎ、長けていたのが、兄であり、その兄が、当面の目標であり、一番のライバルとのことだ。
「兄貴にできるんなら、自分にもできると思えるんですよね。超えられるかどうかはわからないけど、同じようにやってみたいという思いがあるんです」
時代の波に翻弄されてきた兄弟が、こうして同じ技術を追い求め続けることで、繋がっていられるというのは、すごいことである。
いつできるかわからないというが、西山さんの湯沸かしの仕上がりを見る日が心より楽しみである。
■西山慎二氏の製作工程がご覧いただけます ※音が出ます
9件の商品がございます。